花燃ゆ あらすじ ネタバレ 第6回
2月8日日曜日に放送。
寅次郎(伊勢谷友介)が気になり始めた女囚・高須久子(井川遥)は、寅次郎に差し入れする妹・文(井上真央)の存在を知るなり、面会に来る時を見計らって、初めて文と対面。 文は寅次郎と久子との関わりを始めて知ることに。
亡き父の菩提を弔いたいから、自身が行けない代わりに、高須家に出向いて遺品を手にして来てほしいと文に依頼した。
文は末弟・敏三郎(森永悠希)を連れて高須家に出向くことに。
名門・高須家の立派な家のつくりを目にするなり、文は一瞬躊躇したが、意を決して門を叩いた。
家の者はすぐに開けてくれたが、久子の名を耳にすると、途端に色をなしてあっけなく門前払いに。
落胆のまま久子に伝えることとなった文は、何度も尋ねることを約束。
文は、かの亡き金重輔(泉澤祐希)の形見のボタオと、母・滝(檀ふみ)から教わった手作りのお手玉を久子に託して、野山獄を後にした。
この時の寅次郎はひとり獄の中、一心不乱に読書するだけだった。
いくらか日は過ぎて、寅次郎に関わりのある美しい女囚・久子の存在が、家族の間でにわかに話題となる中、手分けして寅次郎に届ける書物を揃えて行李に入れている時のことだった。
文は、寅次郎ではない達筆の書き付けを目にすることに...。
文が野山獄へ出向いて・獄司・福川犀之助(田中要次)に寅次郎への書物を託してすぐにも、福川の計らいあって、達筆の書付の主である富永有隣(本田博太郎)と文が対面。
文は書付に記された通り、書に必要な筆と墨と硯と紙の一式を、富永に手渡した。
富永は、文の人や物の見る目を讃えて感謝。
かつての明倫館の秀才としての学びを寅次郎から褒められた嬉しさから、獄囚に書を教えているという。
その頃には獄囚の誰もが、『孟子』をはじめとする書の読破に一心不乱の寅次郎に、関心を寄せるまでになっていた。
しかし、肝心の高須家での対面は、かなわないままの日々...。
いつものように、あきらめて高須家を後にしようとした時、使用人と少女から声をかけられて...。
後を振り向いた文は、母・久子と面影の似ている少女に驚いた。
しかし、血相変えて家から出てきた家士から手を強くひっぱられた少女は、家の中へ...。
萩城では、江戸から戻った伊之助(大沢たかお)が、藩主・毛利敬親(北大路欣也)の前に報告。
開国に伴う欧米列強の脅威の中、これからの人材を育てるためにと洋学所の設立を進言する伊之助をはざまに、寅次郎を必要性を主張する周布政之助(石丸幹二)と、脅威は理解しつつも国元の確立を主張する椋梨藤太(内藤剛志)は、相変わらず平行線のまま。
結局のところ、敬親は二人の重臣の主張を理解するも、椋梨の進言を受け入れて、伊之助は明倫館勤めに。
何も変わらない無念な気持ちのままの伊之助だったが、周布の計らいで寅次郎との面会が実現。
ぜひ力が必要とする伊之助に対し、寅次郎は己を磨く必要のあることを理由に、「偉くなれ」との答えのみ。
やむなく野山獄を後にしようとする伊之助は、寅次郎に書物を差し入れに来た文と再会。
心配して気に掛ける文だったが、伊之助は浮かない顔のまま近いうちに杉家に挨拶に行くからよろしくと口にして、立ち去るだけだった。
それから数日が過ぎて、福川が杉家を訪ねてきて...。
高須家の人が久子への面会に行くという。
福川に伴われて文は面会に立ち会うことに。
面会に来たのは、久子の面影のある少女、すなわち久子の実の娘・糸(川島海荷)だった。
久子の想いかなって安堵する文だったが、糸は久子にもう二度と関わらないでくれの一言を伝えただけ。
そして、糸は険しい表情で、語気を強めながら話した。
父が突然亡くなってからの母・久子は、寂しさを紛らわすためか歌舞音曲に溺れた挙句、三味線弾きとの不貞と密通にも溺れたという咎で、野山獄に入獄したとのことだった。
悲しげな文は、こうすることでしか対面できない久子の想いを、糸に切々と口にして...。
しかし、久子はそれを止めると、糸の気持ちを受け入れて、そのまま獄へ入るだけだった。
いてもたってもいられなくなった糸は、久子の獄に駆け寄り、格子を強く握りしめて泣きながら生涯恨むと口にして...。
糸の手に久子は優しく自身の手を添えたも束の間、糸は涙ながらに振り払って、野山獄を出て行った。
それから数日が過ぎて...。
文と伊之助が出向いた野山獄では、中庭で寅次郎が『孟子集註』を基に、獄囚を前に講義を施していた。
野山獄が活き活きする様子に、文と伊之助は明るさを取り戻してゆく。
孟子は人が本来の人としてのあり方を説いている、という定評あって久しく...。
2014(平成26)年1月18日土曜日発売の『「孟子」一日一言 吉田松陰が選んだ「孟子」の言葉』(吉田松陰・川口雅昭 / 致知出版社) には、獄囚たちの心を打ち、牢獄が学び舎になってゆく流れが、克明に記されており...。
吉田松陰直々の解釈があるのは嬉しかった。
ただ鵜呑みにするだけでなく、過去の書物を批判的に読む態度も伝わってきて、この吉田松陰の解釈こそが大切だなと実感した一冊。
「至誠にして動かざる者は未だ之れあらざるなり」(本書77頁)
吉田松陰直々の言葉を最後に、門人たちに示したという件には感動。
この度の第6回終盤で観られた展開そのものが記されているかのようだった。
獄囚であれ、学び舎にて活き活きと学ぶ姿には、感動を覚えるもの。
『やまぐち寶楽庵』のかねてからの持ち味である和菓子の差し入れがあれば、嬉しいだろうなあ。
懐かしい深い味わいのやわらか団子【吉田松陰串だんご 12串(24個)】 。
さつま芋の餡入りの一口饅頭の【吉田松陰の妹 文(ふみ)のすいーつだより 16個入り】。
ホワイトチョコとアーモンドの美味しさが広がるサクサクの軽いサブレの【吉田松陰の妹 文(ふみ)のおもてなし サブレ18個入】。
吉田松陰を塾長、実妹・杉文を女幹事、すなわち後の松下村塾の原型ということになるのかなあ。
2014-12-31 |
共通テーマ:日記・雑感 |
nice!(0) |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
編集
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】「孟子」一日一言 [ 吉田松陰 ]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0264%2f9784800910264.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0264%2f9784800910264.jpg%3f_ex%3d80x80)


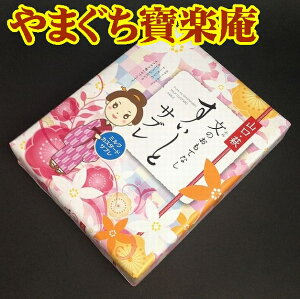
コメント 0